田舎への地方移住が2ヶ月後に迫り、いよいよダウンシフトへのカウントダウンが始まった。これが実現すれば、僕は晴れて「ダウンシフターぬるいぬ」となる。
そんな今日この頃、ふと思い立って図書館で気になっていた本を借りてきた。アメリカの社会学者 ジュリエット・B.ショア著の『浪費するアメリカ人 なぜ要らないものまで欲しがるか』である。
この本、あまりに難しくて読むのに難儀したのだけど、僕なりに読み解けた部分をもとに思索に耽ってみようと思う。
- ダウンシフトの意味と背景
- 『浪費するアメリカ人』(ジュリエット・B.ショア著)の教え
- 日本でダウンシフトを実践するヒント
ダウンシフトの意味
まず、前提として「ダウンシフトとは何か?」を簡単に説明しておく。
もともとは車のギアを“低速に切り替える”という意味で使われる言葉。別名を「減速生活」とも。過度な出世競争や長時間労働、経済成長至上主義から降りて、自分の好きなことに取り組んだり、家族とゆったりした時間を過ごしたりすることに豊かさを見出すライフスタイル。
ショアは、書籍の中でこの考えを提唱した。
よく聞く言葉として、FIREとかセミリタイアなどがあるが、これらとは少し性質が異なるようだ。
◎FIRE
経済的自立によって早期退職を目指す考え方。投資などで生活費を賄い、働かずに自由な時間を得るのが目的。資産形成重視のライフスタイル。
◎セミリタイア
ある程度の貯蓄や投資収入を得て、「働かなくても生活できるが、少しは働く」状態を目指す。補助的・趣味的な意味合いで働く。
◎ダウンシフト
お金よりも心の余裕や自然との共生、人とのつながりなどを大切にし、「あえて収入を減らしてシンプルに暮らす」方向に舵を切る。
セミリタイアとダウンシフトは似ているように感じるけど、セミリタイアは資産ベース、ダウンシフトは思想ベースという点で異なる。
ダウンシフトは、資産形成や節約術的ノウハウにはあまり傾倒しておらず、「生き方そのものを再設計する」という考え方に近い。モノよりも時間、お金よりも自由を大切にする思想だ。
『浪費するアメリカ人』が描く“豊かさの錯覚”
この本のテーマは「なぜ物質的に豊かになっても満たされないのか」という問いである。思えば長い間、僕はこの謎に苦しめられてきた。
自分のお気に入りで満たされた部屋に心が充足するのも束の間、気づけば別の何かを貪るように買い求めていた。仕事のストレスを解消するために、そうせずにはいられなかった。気づけば僕の部屋は、読みもしない本や使わない家具で溢れかえり、洋服なんかは明らかに過剰に所有していた(それは今もだけどw)。
その結果、月末のカード請求に追われ、長時間労働から逃れられなくなっていった。毎月のように赤字決算となり、わずかなボーナスでその補填をするような自転車操業が繰り広げられることになったのだ。いと悪ろし。
ショアは、アメリカ人が豊かになったにもかかわらず幸福度が上がらない理由を、「社会的比較」という構造から説明した。
上へ、上へとずれる比較軸
かつて人は「自分の隣人」と暮らしの質を比べていた。
しかし今では、テレビ・広告・SNSの発達により「上の層」の暮らしを日常的に見せつけられる時代になった。
その結果、人々の基準は上へ上へと引き上げられていく。
「もっと稼ぎたい」「もっと買いたい」「もっとよく見られたい」。
この現象をショアは「アップスケーリング」と呼び、中流層の多くが「見えない競争」に巻き込まれていく様子を描いている。つまり、人間の底なしの欲深さが悲劇の種となっているということだ。
そして、僕らの周囲でもこの現象は日常的に起きている。インスタの投稿、YouTubeのライフスタイル動画、それらが日常の比較対象となり、人々は静かに欲望を刺激され、疲弊していくのである。
働いても満たされない社会
ショアは「ワーク・アンド・スペンド・サイクル(働きすぎと浪費の悪循環)」という言葉で現代人の矛盾を描いた。
これは簡単に言えば、「働けば働くほど消費が増え、消費が増えれば、もっと働かざるを得ない」という構造を表している。うーん、実に耳が痛い。どれだけ収入を得ても、それに合わせて支出も膨らんでしまうというワケだ。
この構造の恐ろしさは、誰もがそれを「進歩」や「成長」の名のもとに疑わない点にある。いい仕事をして、いい給料をもらい、いい家に住み、いい車に乗ることこそが正義だと信じられている。
とあるビジネスマンから「現状維持は退化と同義である」という言葉を聞いたことがある。多分、何かの受け売りだとは思うのだけど、完全に経済成長至上主義に侵された思想だと感じている。正直、僕には全く理解できない言葉だった。
便利さや快適さを得た代わりに、僕は知らず知らずのうちに労働に人生を支配され、自分の時間を失っていったのだ。
ダウンシフトという静かな革命
ショアが見出した希望は、そこから降りる人々の存在である。
彼女は彼らを「ダウンシフター」と呼んだ。
彼らは年収にこだわらない。モノの量よりも、時間の質を重視するし、ブランドよりも、自分のリズムを尊ぶ。
この思想は、現代日本の「半農半X」や「スローライフ」とも深く響き合う。都市の速度から距離を取り、自然と共に、自分のペースで生きる。それは、逃げではなく、再定義であるといえる。
僕は、このダウンシフトを、これからの人生で実践していこうと考えているのだ。
日本におけるダウンシフトの潮流
ここ数年、「働かない勇気」や「脱消費社会」といった言葉が注目を集めている。
背景には、長時間労働・過剰な比較・情報過多という三重苦がある。
それらに対応するための手段として、次のようなものが挙げられる。
- 半農半X:農的暮らしと創作・副業を組み合わせた柔軟な生き方
- ミニマリズム:モノを減らすことで暮らしと心を整える思想
- スローライフ:都市のスピードから一歩引き、生活のリズムを取り戻す
いずれも共通しているのは、「多くを求めず、自分に合う適量で生きる」姿勢である。それは経済的なダウングレードではなく、むしろ意識のアップグレードと言える。
ダウンシフトを実践するための3ステップ
- 消費を見直す
本当に必要なものかどうか、一呼吸置いて考える。 - 働き方を緩める
在宅勤務、副業、短時間勤務など、時間の主導権を取り戻す。 - 余白を作る
予定を詰め込まず、「何もしない時間」を意識的に確保する。
この3つを始めるだけで、生活は少しずつ変わり始める。忙しさの中に埋もれていた“自分の声”が、また聞こえてくるだろう。
僕の場合、1と3については人付き合いや買い物などの誘惑が多い都心を離れて、物理的に消費から距離を置くことにした。その手段が、地方移住である。
荒療治ではあるが、それくらい強制的に消費を避けなければ、俗世に塗れた僕は平気で時間やお金を浪費してしまう。意志が弱いのだ。Amazonなどのネットショッピングには注意しなければならないけど。
2に関して言えば、極端だが会社員という働き方そのものを辞めることにした。
20年弱かけて試行錯誤した結果、会社にいながら働き方を調整するのは不可能だと痛感したからだ。
会社からは、常に成長と利益の追求だけを求められた。申し訳ないけど、誰も僕の人生のことなど考えていないと感じざるを得なかった。
今後は培ってきたスキルを活かして、わずかばかりの生活費を稼ぐつもりにしている。
減速する勇気
人は「速さ」に酔う生き物だ。けれど本当に必要なのは、スピードを落とす勇気だと思う。「もっと」ではなく「もう十分」を選ぶ力。働くこと、稼ぐこと、消費すること。その意味を問い直し、新しい自由を手に入れる。
ダウンシフトとは、諦めではなく人生の再起動だと思う。
他人の時間ではなく、自分のリズムで生きるための思想なのだ。
まとめ:人生の速度を下げて、豊かに生きる
豊かさとは、速度ではなく深度である。
急いで得たものは、すぐに消える。
ゆっくり味わったものだけが、心に残る。
ダウンシフトは、その「深さ」を取り戻す行為だ。
静かに減速すること。それが、現代における僕の最適解である。

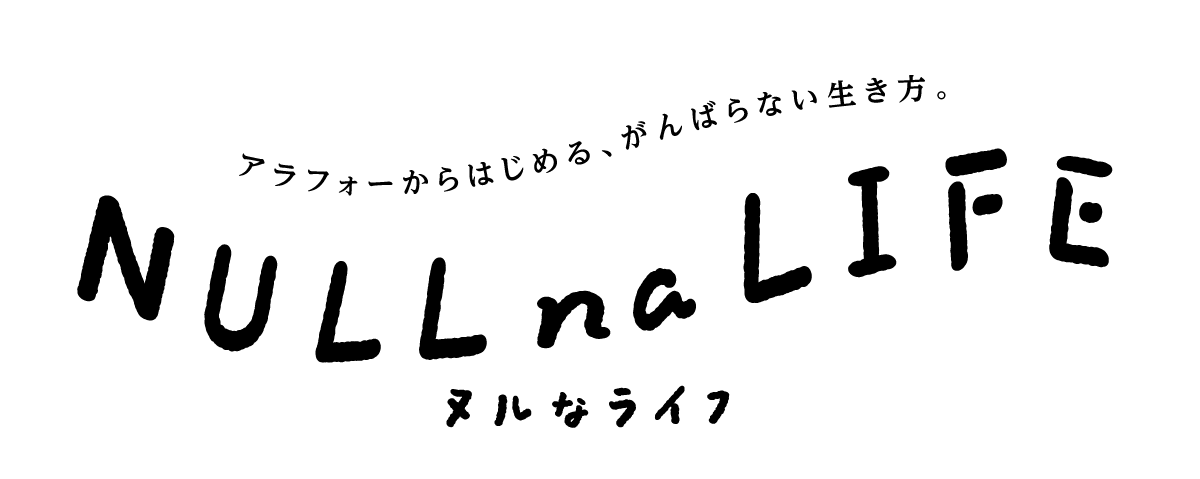
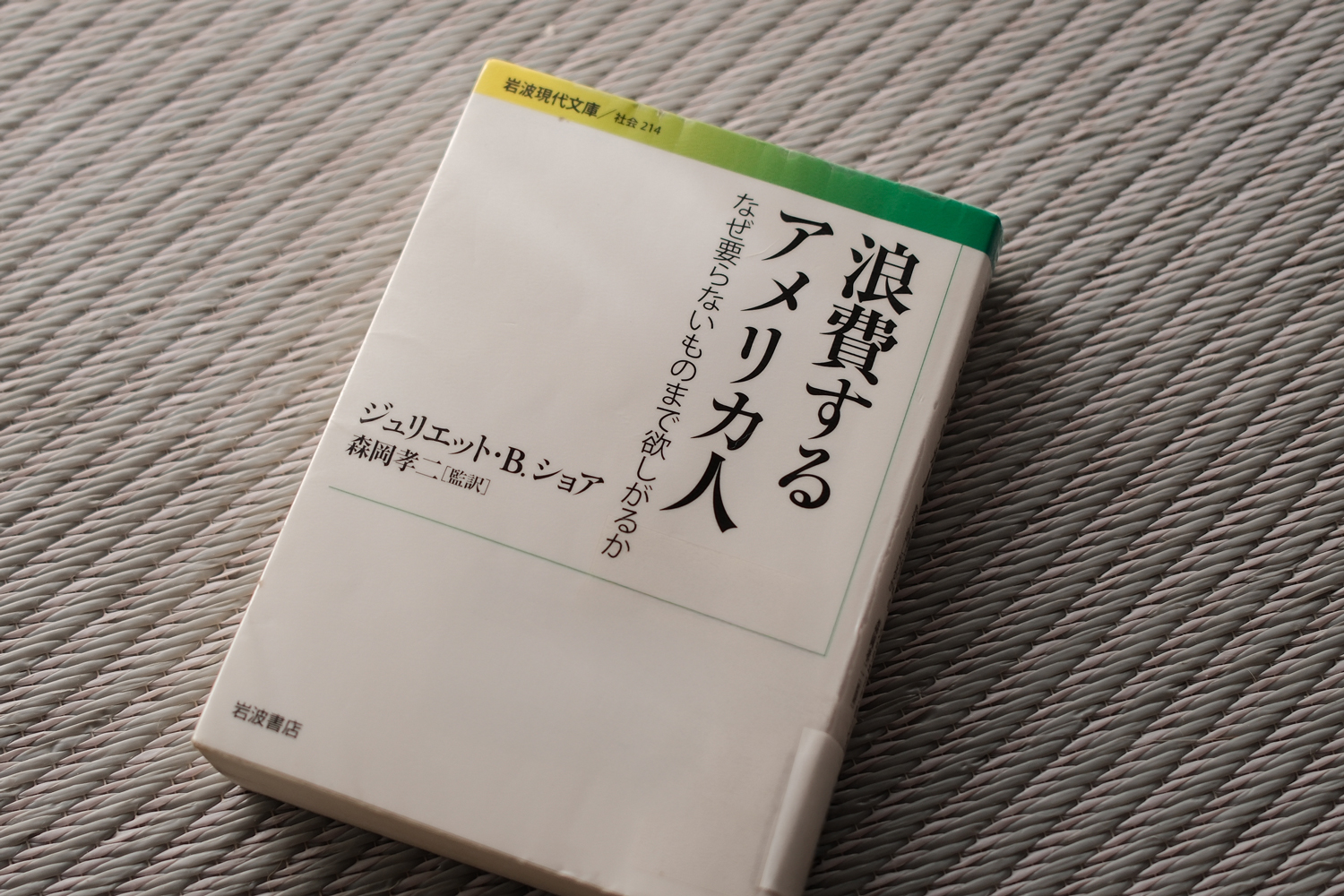

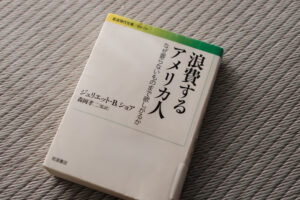










コメント